
2012年2月オープン!! (京阪奈学研都市町づくり・交流会)
展示品:竹取物語の舞台となった山本駅跡や筒城宮、月読神社
「かぐや姫」に関連するもの。日本や世界の民俗・考古資料等。
特色:古民家を再生利用!! 土蔵や古材生かした内装!!
設立目的: 国民の教育、学術、文化発展に寄与する。Taketori okina Museum
"かぐや姫の里”京田辺竹取翁
博物館
![]() 芳泉作
芳泉作
2012年2月オープン!! (京阪奈学研都市町づくり・交流会)
展示品:竹取物語の舞台となった山本駅跡や筒城宮、月読神社
「かぐや姫」に関連するもの。日本や世界の民俗・考古資料等。
特色:古民家を再生利用!! 土蔵や古材生かした内装!!
設立目的: 国民の教育、学術、文化発展に寄与する。Taketori okina Museum
”竹取物語の里”京田辺
かっ
一、「竹取の翁」の家は、「山もと」の近く
『竹取物語』の話は、今まで架空のものであり、きわめて伝説的・浪漫的に構成された虚構の物語であるとされてきた。
しかし 私は、竹取の翁がいたのは、京田辺市ではないかと考え平成三年度発行の『筒城』第三十六輯に「山城国綴喜郡山本駅と古代駅制について」の中で少し書いた。その後も研究を重ねるうち、『古事記』垂仁記に「大筒木垂根王之女、迦具夜比売命」が記されていて「かぐや姫」は実在の人物であったことがわかり、その「大筒木垂根王」の墳と伝えられる古文書も地元で見つかった。そこで、この田辺が『竹取物語』発祥の地であり「かぐや姫」伝説地という結論に達した。
京田辺市普賢寺の「大筒木垂根王」か山本駅の駅長それに延喜式内佐牙神社の太夫が、『竹取物語』に登場する翁であり山本駅一帯が“竹取物語の里”と考えている。
『竹取物語』 物語の原文では。
みかどおほせたまはく「みやつこまろがいへは、山もとちかくなり。
みかりのみゆきししたまはむやうにて、みてむや。」とのたまはす。・・・
と記され。現代語に訳すと
帝が迎せ下さるには「造麻呂の家は、山もとの近くに
ある。
御狩の行幸に行くような振りをして見てしまおうか。」とおっしゃる。
とある。
帝がいうのには、竹取の翁(造麻呂)の家は、「山もと」の近くにあるとしていて、狩の行幸に行くような振りをして「かぐや姫」を見に行こうか、と記されている。
私は、『竹取物語』の出来た頃の「山もと」と言う地名は、和銅四年(七一一)に古代駅制の「山本駅」と言う駅家が存在していたことから有力であると考えた。日本全国に沢山存在している「山もと」というのは、今まで「山の麓」という意味であるとされてきました。しかし、京田辺市三山木の山本集落は、固有名詞として『竹取物語』が出来た以前からあり、現在も存在している歴史上重要な地名であることからも重要視せねばならない。この「山本」という集落あたりに翁の家が存在していた場所と考えている。
大阪府と奈良県とに境を接する京都府京田辺市は、東に木津川が流れ、西に生駒山系が連なるなだらかな丘陵地となっている。ここは京都市と奈良市の中間にあたり、古代から交通の要衝として数々の歴史を物語る多くの文化遺産が点在している。
奈良時代以前には、京田辺市を大和から丹波に至る古山陰道が南北に通じていた。また和銅四年には、現在の近鉄三山木駅周辺に平城京と太宰府を結ぶ古山陰・山陽道の宿所として山本駅が設置された。
平城京に都が置かれた翌年の和銅四年正月、『続日本紀』巻五には、
四年春正月丁未 始置都亭驛 山背國相楽郡岡田驛 綴喜郡山本驛
河内國交野郡樟葉驛(以下略)
と記され、平城京に通じる主要官道の都亭驛として綴喜郡山本驛を新設されたことを明言している。
(詳細については、『筒城』第三十六輯 「山背国綴喜郡山本駅と古代駅制について」を参照)
京田辺市の山本区周辺には、『竹取物語』にちなむ地名として前記の「山本」 の他「山崎」「筒城」「筒城宮」「多々羅」「甘南備山」「月読神社」が存在し、神仙思想が溢れていて天女伝説を兼ね備えた地域である。
京都に平安京が遷都するはるか以前、京田辺市内には、かつて筒城宮といわれる都があった。この筒城宮は、河内の国「楠葉」で即位した継体天皇が五年後(五一一)に多々羅の「都谷」に遷都された所である。
京田辺市近くの甘南備山も「かぐや姫」の名付け親としての伝承地であると考えられる。
物語の中で
この子、いとおほきになりぬれば、名を、みむろどいむべのあきたをよびてつけさす。なよ竹のかぐやひめとつけつ。
とある。
現代語訳では、
かぐや姫が大きくなったので三室戸の神に仕える秋田という人を呼んで名を「なよ竹のかぐや姫」とつけた、とある。
京田辺市郷土史会の水山春男氏によると、
三室とは「神の宿るところ」という意味で、神社のある処を言ったものであり「ミムロ」「ミモロ」といわれるところは甘南備山ではないだろうか。この山は周辺の生駒山脈の山が低いためそびえ立って見え、富士山に似た山容と相まって、神の山と信仰され、大和竜田の三室山、飛鳥の三諸山とともに神(甘)南備山とよばれてきた。山頂には式内社に比定される神南備がある。この神に仕える人ではなかったか。
としている。
また、「みむろど」を固有名詞とすれば京田辺市近くの宇治市三室戸も「なよ竹のかぐや姫」の名付け親としての伝承地であると考えられる。この三室戸は、宇治川東部一帯で古くから竹の産地として知られていて、三室は神在ますところとされている。この地は、京田辺市に近いところである。
二、 「竹取の翁」の名は、「さかき」で「さか」は酒
『竹取物語』の最初は、
いまはむかし、たけとりのおきなというものありけり。野山にまじりて、たけをとりつつ、よろづのことにつかひけり。名をば、さかきのみやつことなむいひける。そのたけのなかに、もとひかるたけなむ一すぢありける。あやしがりて、よりてみるに、
とあり、現代語に訳すと。
今は昔のことになるが、竹取の翁というものがいたものだ。野や山に分け入って、竹を取っては、色々な事に使ったものだ。名前をば、さかきの造となむいったものだ。その竹の中に根元の光る竹が、一本あったものだ。不思議に思って、近寄ってみると、
となる。
竹取の翁の本名「みやつこ」とは、朝廷に仕える人をさし、「まろ」とは男子の名前をあらわしていて、半官半民の両方を受け持った翁であり、古代駅制における駅長のような人でなかったかと思われる。駅長とは、駅制における「駅家」の長として駅務を主宰し、その地方の豪族が任命されていて都の情報をはじめ海外などの色々な情報を知ることができる人物であった。
昔話の民話に登場する翁は「貧民致富」説話を伴っているといえるが、『竹取物語』に登場する翁は「朝廷に仕える人物」だったといえよう。また「竹取翁」説話は、農耕が生産活動の基盤であった時代に、竹細工に関してもすぐれた技能を持っている人達が住んでいたのであり、「竹の呪力」はそれを細工する人々に対する畏敬の念を抱かせたと考えている。
柳田國男は、『定本柳田國男集』第六巻『昔話と文芸』所収の「竹取翁」と「竹伐翁」で、『竹取物語』は日本の民間伝承説話をもとにして生まれたもので、文献上の竹取説話に炉辺で語りつがれてきた口詞文芸を重ねて民俗学的な照明をあてたとしている。
柳田の論究は、竹取り翁の生活について『海道記』の中で、「翁が家の竹林云々」と改めて富裕の翁にしたてているが、本来は野山にまじって居たのであって、布や穀類と換えて貰わねばならぬ者で貧困のどん底にいた者と見ている。その貧翁が一朝にして宝を見つけ稀有の長者になった点に、説話の根本の趣向があったとしている。また、かぐや姫は空へ帰る天界の存在で、鴬姫系の鳥類に身をかえる話型を指摘したうえで、竹取物語が、羽衣説話の何らかの段階を足場にしていると論述していて、それは白鳥処女型の裏付けとなっている、と記している。
さらに、柳田國男の『竹取翁』によると「老翁になるまで、竹を伐りまたは柴を苅っていなければならぬ人、すなわちいたって貧しい者…」と書かれている。
しかし、私は、ここに登場する竹取の翁の名前が「名をば、さかきのみやつこ(造)となむいひける」
とあるところから、 「さかき」(榊)つまり「神に仕え」「朝廷に仕える人物」を題材にしたと考えている。つまり半官半民の両方を受け持った人物であり「竹の呪力」をも兼ね備えた翁と考えた。
その人物は、前記の山本駅の駅長か、当時の山本郷の長老である太夫を登場人物として想定したのではないかと考えている。
また「さか」 は、延喜式内佐牙神社や延喜式内酒屋神社それに延喜式内咋岡神社、山崎神社などに関係した古代酒造りの「さか」 (酒)に関係があって、このように名前をつけたのではないだろうか。
日本に新しい酒造技術をもたらした記録は、『古事記』の応神天皇の条に
(前略) 又秦造の租・漢直租、及酒を醸むことを知れる人、名は仁番亦の名は須須許理参渡り來つ (以下略)
とあり、渡来人(百済人)須須許理が麹で醗酵させて酒を造る技術を伝えている。
これについては、延喜式内佐牙神社の変遷を知ることの出来る文治元年(一一八五)の古文書『延喜式内佐牙神社本源紀』に
(前略) 則朝廷酒司ノ舘舎ニ祭ル所酒殿神ニシテ御名ヲ称シテ佐牙弥豆男神 佐牙弥豆女神ノ二座ニシテ、就造酒司ノ官人等貴ヒ敬所ノ御神也、(中略)唐国ヨリ来朝スル所ノ人在リ、其の名ヲ曽保利弟ト云 曽々保利ト云弐人在リ (以下略)
とあり、
佐牙神社には、酒造用水を守護する男女二神の佐牙弥豆男と佐牙弥豆女の酒殿神がみられ、唐国から酒を造る曽保利と曽々保利という二人が渡来したと記されている。「佐牙」は「サケ」「酒」である。
また、京田辺市飯岡の延喜式内咋岡神社は、酒殿の神を祀り、興戸の延喜式内酒屋神社は、酒を製造した場所とされ、三山木の山崎神社には、延徳二年(一四九〇)の「曾保利弟 曾々保利 蹟 (以下略)」の古文書がある。
このように山本駅一帯は、古代から酒造りの「さか」 (酒)にちなむ神社が沢山ある。

感想・御意見・御希望は、メールにて、是非お願いします!
E-Mai 『竹取物語』研究所竹取の翁・かぐや姫に、お寄せ下さい。
『竹取物語』研究所竹取の翁・かぐや姫に、お寄せ下さい。
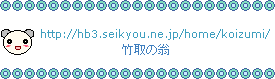
ここに掲載の写真および記事の無断転載を禁じます。
『竹取物語』研究所 代表:小泉芳孝 copyright(C) 1999 Koizumi. All rights
reserved.